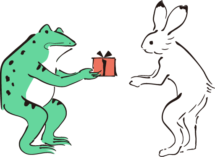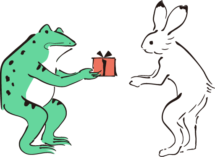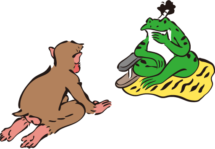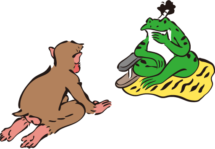こんにちは。中学受験100%ウカルログ管理人ことハンドレッドの友です。今回は算数問題集の使い方について。
一般的な成績アップの方法としては「1冊の問題集を何度も繰り返す」のが常套手段です。
が、①まだ小学生②勉強嫌いーーの子にとって、これは当てはまらないと思うのです。
うちの場合、仮にセオリー通りに、1冊の問題集を繰り返していたら悲惨な結果になっていたでしょう。何十冊も家に問題集があったからこそ、合格を勝ち取れた気がする。

 ハンドレッド先生
ハンドレッド先生その説は一理あります。確かに、やり方次第で成績が下がってしまう可能性もある。
上記ブログでは詳しく触れられませんでしたが、「よっしゃ!複数使いだ!」とばかりにリアクションしてくれる素敵な方々が、やり方を間違えたばかりに成績急降下となろうものなら夜も眠れないわけです。


ですので、今回は主に算数での複数問題集使い、その注意点を追記します。



「問題集のたくさんある家の子ほど成績が悪い」説について
まずですね。
最初に算数問題集を購入した時の心得を。
1、子どもにいきなり渡してはいけない
2、1ページ目からやってはいけない
3、「授業で何を習っているのか」、「子どもの弱点」を親が知った上で活用する
4、全ページをやろうと思わない。あくまで類題を探す目的で使うこと
(※主に算数の場合)



まぁまぁ。それは終了組の特典として堪忍いただければ。
ともあれ、ここを注意しないと、教育雑誌なんかによくある「問題集がたくさんある家の子ほど成績が悪い」パターンに引っかかってしまいます。
最初しかやらない問題集がたまっていく子どもたち
問題集の使い方ダメママを自分なりに想像してみました。設定は5年生の終わり頃ということにしておきましょうか。
ここに算数の苦手な子どもが一人。
その成績に悩む母。ママ友に相談すると『塾技』という問題集を勧められた。
思い立ったが吉日を善とするアクティブ母は中身を確認することなくそれを購入。その日のうちに子に渡す。
「〇〇ちゃんはこれやって成績上がったんだって」。子は「うん」とか、「ああ」とか言ながら、パラパラパラパラめくっていた。
しばらくすると、子は最初の問題を解き出した。母は満足して夕食の支度に取り掛かる。
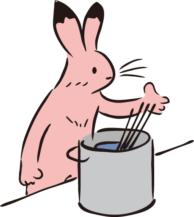
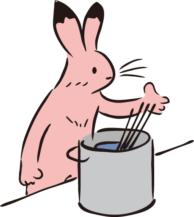
けれど、次の日「塾技」は本棚の中にある。1週間後も本棚の中。やった形跡があるのは最初のページだけ。
母が怒ると「だって、難しすぎるんだもん」
母は改めて「塾技」をめくる。なるほど、確かに難しそうだ。その上、ママ友の子どもは麻布志望。母の選択は失敗だった。
アクティブなタイプゆえ、その日のうちにママ友に連絡し、やさしめの問題集はないかと尋ね回る。「『裏ワザ算数』とか『ベストチェック』は?」


真新しい問題集は子も嬉しい。
子は『ベストチェック』をぱらぱらめくり、最初のページをやってみる。その後に『裏ワザ算数』も最初の方をやってみる。
母はその様子を見届けて、小3の妹をスイミングスクールに連れて行く。
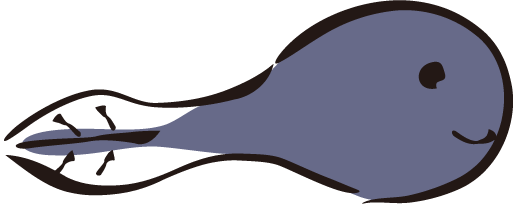
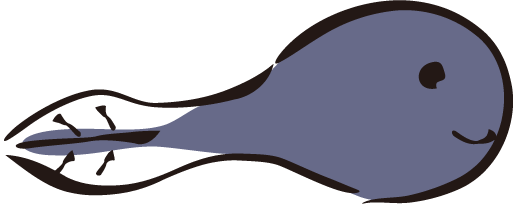
次の日、子は『ベストチェック』の2ページ目をやっていた。『裏ワザ』はやっていない。
その次の日は『ベストチェック』の3ページ目をやっていた。『裏ワザ』はやっていない。その次の日は2冊とも本棚の中。1週間経過しても本棚の中。
母は怒る。せっかくやさしいものを揃えたのに。「だって、裏ワザなんとかは説明が多すぎるんだもん」
言われて母も中をめくる。確かにそうだ。問題集というより、参考書みたいではないか。
「だけど、ベストチェックの方は説明が少ない。わかんない問題は答えみてもわかんないまま。だからやっても意味ないし」
なるほど、確かに。意外にロジカルな言い訳に母はそうかと膝を打つ。


やっぱり、子どもと一緒に選んだ方がいい。
次の日曜、アクティブ親子は本屋に行く。そうして子どもの気に入った「アレ」と「コレ」と「それ」と「あれ」を購入する。
ーーー
そうして、それから三か月後。本棚には殆ど使っていない問題集が何冊も並んでいる。キレイだしメルカリできっと高く売れるはず、母は自分を慰めている。



通塾組にとって市販問題集の目的は類題探しです
このお母さんはおそらくいい人だと思うのですよ。そんないい人を糾弾するのは気が進まないのですが、これでは子の成績は上がらないでしょう。
まず、買った問題集を子にいきなり渡すのがダメです。普通の子どもは問題集を与えられても効果的に使えません。パラパラめくって印刷の匂いをかいで終了。



1ページか、2ページか、3ページくらいはね。そうやって最初の数ページしかやっていない問題集がたまっていくわけですよ。
前段でのハンドレッドおっしゃる通り、最初の「計算問題いろいろ」や「つるかめ算」を延々と繰り返し、永遠に「速さと比」や「相似」にはたどり着けないのです。


そもそも問題集は1ページ目からやる必要はありません。というか、やってはいけません。
これについては「複数の問題集を解いた方がいい話」でも書きましたが、最初からやる必要があるのは学校や塾のテキストだけなのです。



苦手なところから、です。あるいは、今、授業で扱っているところからです。
塾のテキストがメーンで、市販の問題集はあくまでサブ。なので、全部解く必要はありませんし、極端な話、苦手な「速さ」の単元のみ使って終了でもよいのです。
「なるほど。確かに。では、子どもに伝えよう」、先のアクティブ母さんなら思うかもしれません。ダメです。
塾のカリキュラムと照らし合わせつつ、まずは母が問題集の全体像をつかむのです。そうやって「子どもがどこを解くのか」を日々指定していくのです。
言っておきますが、ここから先は誰もが嫌う「~ねばならない」話に終始しますよ。「子の自主性を重んじる」術は忘れましょう。


意外に思われるかもしれませんが、普通の子どもは塾の授業で何を習っているのか、よくわかってはいないのです。
「そんなバカな!」と衝撃を受けるかもしれませんが、一度授業後に「今日、何を習った?」と尋ねてごらんなさい。
突っ込んだところで、「えと、図形のなんかへんなの」とか「三角形のいろいろ」とか要領を得ないはずなのです。
もし、お子さんが、「高さが等しい三角形の面積をやった」と当然のように言えたのなら、子の自主性を重んじてもよいでしょう。
そうではない場合、塾テキストならいざ知らず、使い慣れない問題集から該当箇所を探すのは難しいはずです。以前、それをやらされた知人の子は探すだけで40分くらい掛かっていました。



そうなのです、複数使いで成績を上げるのは「言うは易し、親が面倒」という弱点があります。
親の方にも慣れが必要で、子が何を習っているか、ちゃんと把握しなくてはなりません。子の苦手をちゃんと把握しなくてはなりません。



本来は、それがベストだと思いますよ。塾とは違う問題集を見ることで子どもは自分が何を習っているのか、客観視できるようにもなりそうです。
苦手分野ならなおのこと、自分で弱点を認識するのが一番です。それに慣れれば、中学以降の自学自習もうまいこと運ぶようになりましょう。
かくいう、うちでは成功しませんでしたがね。
何十冊もの問題集をチェックする?いや、ムリだわ、そんなの
さて、子の誘導に失敗した自分は中学受験中、類題探しに明け暮れました。
子が「授業でできなかった」「問題集でできなかった」「テストでできなかった」類題を片っ端から探すわけです。
そうこうするうちに、問題集は十冊、二十冊、三十冊と増えていき、本棚は中学受験がらみの書物でいっぱいとなりました。
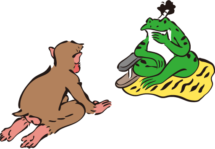
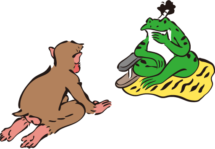






確かに。おっしゃることはわかります。
この真似を世の親が全員やろうものなら経済活動は停滞しそうでしょう。それでなくとも、母は忙しいのですからね。
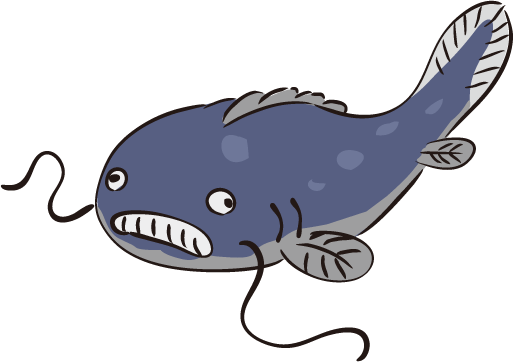
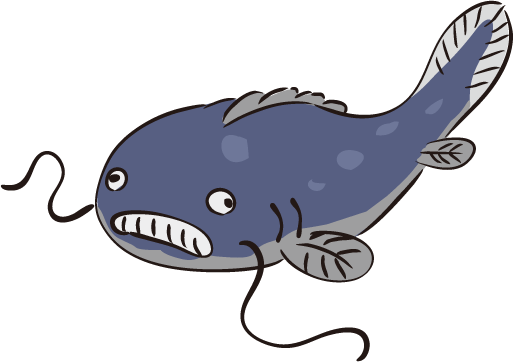
といえ、問題集効果を最大限に発揮するには親の手助けは不可欠です。渡しっぱなしでは「やらないよりマシ」くらいの成果しか得られません。
キレイな問題集がどんどん増えて「親のイライラが増す」だけの費用対効果マイナスにもなりかねないし。
だからといって、本棚いっぱいは趣味のレベルでしたね。
何十冊もの問題集をチェックして、類題20問とか30問とか探すだなんんて、なんとまぁ。今なら絶対ムリだと思う。



そこまでやらなくとも、せいぜい4、5問の類題を繰り返すのでも良かった気もするわけですよ。
3回やってもできない問題というのは、だいたいその時期にはキャパオーバーなんですよね。10回やってもできるようにはならない。
こういっては元も子もないのですが、その時点では繰り返しても結局、出来るようにはならず、忘れた頃に、突然出来るようになったりするものです。


類題探しで算数偏差値60までなら上げられる
ですので、せいぜい数冊程度、数問程度の類題を繰り返すくらいでもいい。繰り返しの際は3回やって出来ない問題は潔く捨ててしまっていいと思います。



おっしゃる通り。類題でも毛色の変わったものを混ぜ込んだりはしました。
ちなみに、数字変えの類題を課すような塾の場合、親が調整しないとパターン学習まっしぐらです。
だからこそ、塾のテキストまで把握しておくことが大事だったりする。






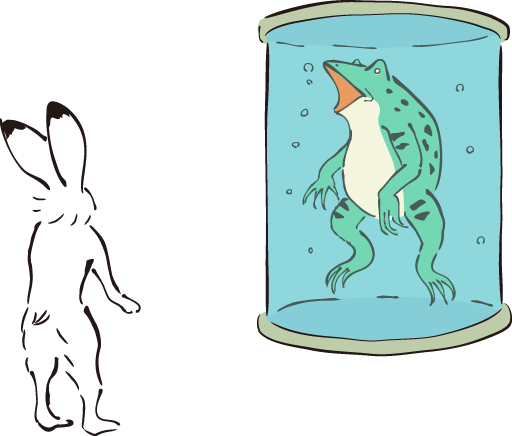
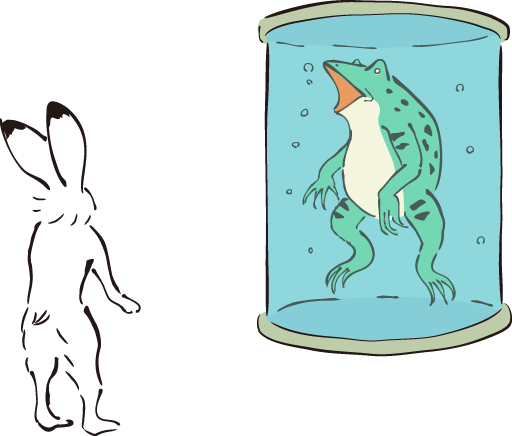
というけど、テキストを把握してないと類題なんか探せないわけですよ。
問題集の効果的な勉強法を突きつめると「中学受験は親が9割」を地で行く感じになるのですね。
今スマホの前で「げっほー」という顔をしているあなた、気持ちはわかります。ただ、やっただけの分の効果は保証します。
算数の偏差値40を50に上げたいのなら、類題チョイスで間違いなく上がります。
偏差値50を60に上げることも大変ですが、可能です。
一方、偏差値60を65以上に上げたい場合や過去問の点数を上げたい場合。類題の繰り返しだけでは難しいです。
入試問題で類題を探そうとやっきになったこともありますが、どうもうまくはいきませんでした。





そうなのです。
とはいってもね、6年アタマまで親がそうやってがっつり助走をつけてやれば、あとは勝手に転がります。その頃までは子ども本人に入試問題に対抗できるような土台ができてきます。
というわけで、複数問題集、類題使いが有用な時期は6年の初めくらいまで。新しい問題集を購入するのもこの時期くらいまでかと思いますね。





中学受験、振り返れば辻褄の合わないことを時にやってしまうわけですよ。
なお、類題を探すのは最初は時間が掛かるかもしれませんが、われわれは大人です。数週間から一か月もすれば、中学受験経験者でなくともコツはつかめてきます。
経済活動や家事活動にもそこまで影響を及ぼさなくなると思いますよ。
1、子どもにいきなり渡してはいけない
2、1ページ目からやってはいけない
3、「授業で何を習っているのか」「子どもの弱点」を親が知った上で活用する
4、全ページをやろうと思わない。あくまで類題を探す目的で使うこと
5、成績上昇の上限は偏差値60まで
(※主に算数の場合)
※当ブログがkindle本になりました。偏差値40台から逆転合格した勉強法です↓