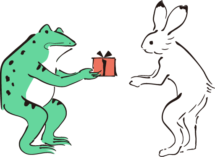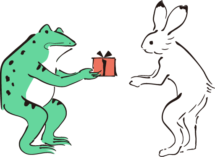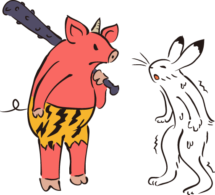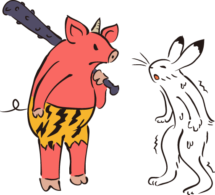こんにちは。100%ウカルログ管理人ことハンドレッドの友です。今回の命題は中学受験生の読書、国語の成績に関わる読書について。
 ハンドレッド先生
ハンドレッド先生結論からいえばイエスですが、中学受験においては「本好きなのに国語はイマイチ」「本読まないのに国語が得意」な子もいたりするのがまた事実。
一方で、「本読まないし、国語も苦手」だとすれば、どうにか読書に親しませたくなるのも事実であり。
というわけで、今回は
①実体験による「読書と国語力」の相関関係→②「本嫌いな子を本好きにする消費イベント」→それでも③本を読まない子が「国語力を上げる方法」→さらに④「本好きなのに国語イマイチなパターン」→なかでも⑤「説明文の得点法」を提案したいと思います。


かゆいところに手が届くこの構成っぷり! ですが、若干長いですよ。なので、必要なところだけスキップして読んでくださいまし。
入塾前のお子さんから小学校5年生のお子さんを持つあなたには多分に有益なテーマとなるかと思います。また、6年生ならラストの「苦手説明文を得点源にする方法」あたりはぜひ。
※本編は既出「読書しないと国語の成績は上がらない?低学年の勉強も紹介」を2つに分け、それぞれ大幅に加筆修正したものです。
低学年で読書をした娘は国語が得意だったか?
唐突ですが、私は活字中毒の母親です。子にも中毒と言わずとも「本好きになって欲しい」という願いがありましてね。
幼児期から低学年にかけ、あれやこれやと読ませておりました。
麻布学園の国語の先生が書いた本はブックガイドも豊富で、何度読み返したことか。未だロングセラーになっていますが幼児向けバージョンも出版されている模様。



このブログの7割くらいはヘッポコ成績についてですので、今回ばかりは自慢させていただきますよ。4年生の時は国語のみ最上位クラスでした。
低学年の頃に意識してやったことは「読書と作文」でしてね。読解問題は一切やらせませんでしたので、読書が多少の影響を与えたのは確かかと。
5年、6年は波があったものの、志望校の過去問はあっさりと合格者平均点を超えました。なので、得意だったと言ってよいでしょう。
娘に関して言えば、思いつく読書の効能は以下です。読んだ本が小説ばかりなので「物語文への効能」という言い換えもできますが。
『たくさん本を読んできた結果』
一、活字に圧倒されることがない
二、本文を読むスピードが速くなる
三、登場人物の言葉に隠された別の意味を読み取りやすくなる
四、情景描写から主人公の気持ちを想像しやすくなる
五、起承転結など物語の型を知ることで、読解問題にも対処しやすくなる
特に「読むスピードが速くなる」ことは、わかり易く確実な利点でした。
国語の入試問題は5000字が平均、長いところで8000字ほど。ゆっくりチンタラ読んでいますと最後の問題まで行きつきません。
国語の過去問に関し、そこまで苦しみが少なかったのは子の読書習慣が大きかったと思っています。
読まない子向けのイベント「本買い放題祭り!」



根っからの「本嫌いな子」はいないと思います。ただ、「親が読んで欲しい本を好まない子」は多いかもしれません。
娘にしても本のチョイスはベタにもほどがありました。本屋に行くと持ってくるのは「グレッグのダメ日記」とかね。グレッグの毒っ気は私も好きですよ。でもね。毎回それだとがっくりですよ。
グレッグでなければ、「ジャングルのサバイバル」とかね。



娘は小学生なら一度は手に取ったことのあるシリーズばかりを好みました。親としては小3とか小4で「やかまし村の子どもたち」とか「星の王子さま」とかに心酔してほしかったわけです。けれど、そうした美しいエピソードは誰もが持てるわけではなく。
よく言われるように、読書は強制するものではありません。
しかし、国語の時間の読書感想文に『サバイバルシリーズ』を選ばれた日はトホホにもほどがあります。
結論からいえば、読書を強制いたしました。
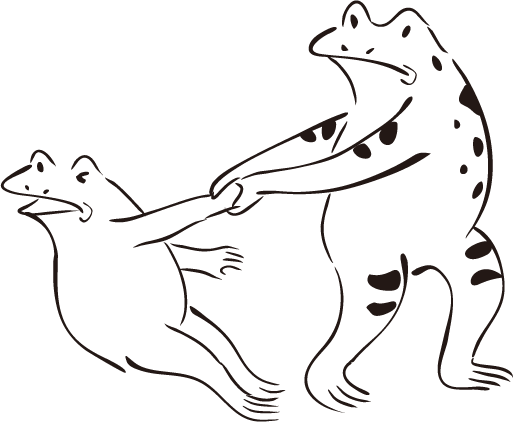
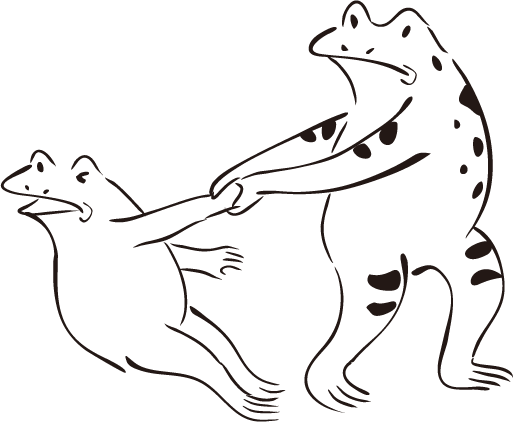
もちろん、多少の策は練り、強制とはいえ「楽し気なイベント」に見せる工夫はしましたよ。
GWや夏休みの前など、一緒に本屋に行き2時間くらい掛けて「本買い放題祭り」をしました。買い放題といっても実際には10冊まででしたがね。3冊は子が好きな本を選び、あとの7冊は母の選りすぐり。
選りすぐりでも、ミヒャル・エンデの『モモ』とかリンドグレーンの『長くつ下のピッピ』とか親が好きそうな7冊ばかりではダメですよ。
小学生が好きそうなもの、たとえば、「子どもたちだけで悪い奴らをやっつけるような話」や「ダメダメ小学生が魔法の薬でなんでもできるようになる話」だったりね。
「痛快コメディもの」「現代もの」「日本の小学生が主人公の話」は本嫌いの子にもとっつきやすいテーマです。それらを軸とし、岩波少年文庫の類は一冊入れるか入れないかくらいがよいと思います。


ちなみに、購入場所はブックオフでもよいのですが、子が「本好きではない」「しかし、新しいものは好き」という感じのよくないタイプならば新刊をおすすめします。



ともあれ、母の選りすぐりを一冊でも気に入ればしめたもの。
それがシリーズものなら続きを与え、そうでないのなら同じ作家の作品、同じジャンルの作品を再び探し与えましょう。
うちの場合は「僕らの7日間戦争」系のシリーズや「都会(まち)のトム&ソーヤ」は本人が気に入り、読破することになったような。
物語の面白さに目覚めたなら続編はブックオフでもメルカリでも大丈夫。そうやって短期間に10冊くらい読むと読解スピードは飛躍的に向上します。
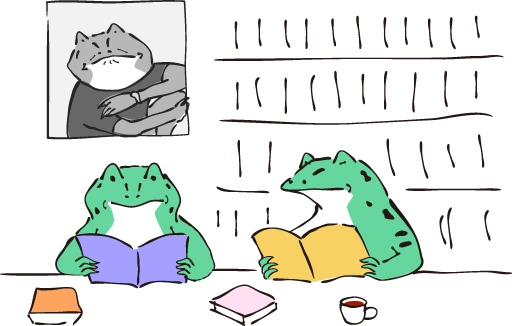
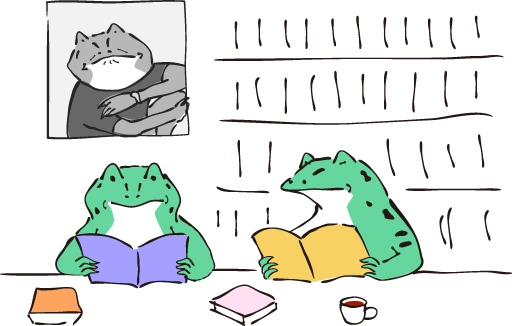
いずれ本に飽き、ゲームや漫画に戻る時期も来ましょうが、それでいいのです。次の長期休みにまたトライしましょう。
国語力は読書でしか鍛えられないのか?



本好きな子は親の趣味に関わらず、勝手に好きになるものでしょう。
けれど、今現在、子が本を読まない、それを懸念する親の方も実は読まない。これはなかなか根が深い。本を選べと言われても親の方もわからない。
そのような親御さんは前段でアップした「本嫌いな小学生でも読みたくなる本」を参考にしてください。



買ったその日のみ、ワクワク頁をめくっていたものの、翌日になったら見向きもしないとかね。あるいは、自分で選んだグレッグだけ読んで、ママが選んだ痛快モノは何故か読まないとかね。小学生向けの楽しそうな本を選んだのにね。
10冊も買ったのにこういう事態になりますと、私を逆恨みしたくもなりますでしょう。


ただですね。
人生が読書ばかりでないように、国語力もまた読書ばかりではないのです。
前半で「国語の成績アップに読書は一役買った」と書きました。しかし、その意味するところは「読書しなければ、国語の成績は上がらなかった」ということではないのですね。



おっしゃる通りのハンドレッド。
知人の子に読書をまったくしない子どもがいました。
本棚には『りぼん』や『ちゃお』ばかり。端っこの方に漫画みたいな挿絵の、字の大きな児童書が1、2冊あるだけ。
しかし、その子の作文能力は嫉妬するほど高かったのです。
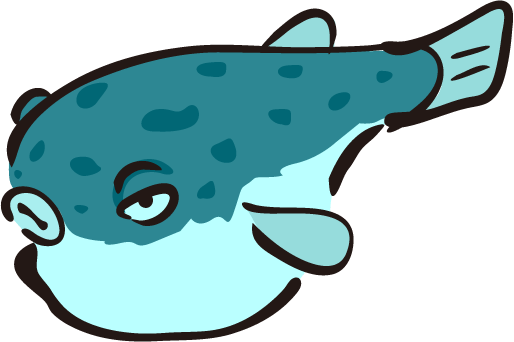
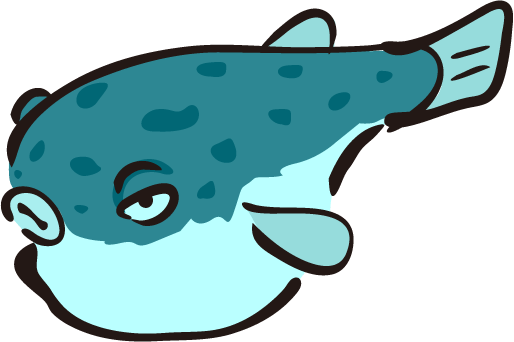
そういう子は他にもいました。漫画しか読まないのに、国語偏差値が他の三教科に比べ10以上高いとかね。
特に女子は他人の心情に敏感であることも前提にありましょう。女子同士のコミュニケーションの中で言葉の表と裏を学んでいるとでもいうのか。



もちろん、方法はありますよ。
先に記しました『たくさん本を読んできた結果』の効能ですが、一、二はともかくとして。
三、登場人物の言葉に隠された別の意味を読み取りやすくなる
四、情景描写から主人公の気持ちを想像しやすくなる
五、起承転結など物語の型を知ることで、読解問題にも対処しやすくなる
三から五までは、漫画でも、アニメでも、映画からでも、読み取れるのではないかと思うわけです。
物語の型も、主人公の気持ちも、本独特のものではありません。よって、その部分は読書以外でも十分鍛えられるのではないかと思うわけです。さらにいえば、人間関係でもね。大人との会話でもね。
一方、国語が取れない子は大量の活字に苦手意識があるものですが、中学受験の3年間、読解問題を解き続ければ、やがて慣れてくるでしょう。



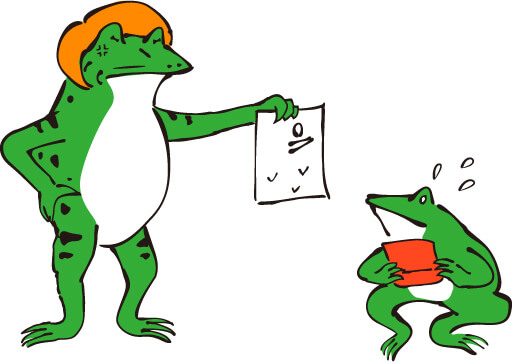
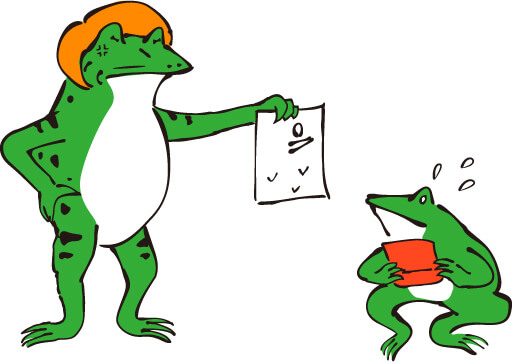
とは、いかないとは思うのですがね。
本好きなのに国語はイマイチになる理由



それについては、いくつかパターンがありましょう。
「イチャモンつけ」こそ読解力を上げる読み方
正直なところ、読書に即効性はありません。読書家の小学生が「成績面で効果が現れるのは中学生以降」だという専門家もいるほどです。
もちろん、個人差もありますし、短期集中型でガッーと読んで「物語の型」のようなものを会得する子どももいるでしょう。
ただ、今現在「本好きなのに国語がイマイチ」ならばスロースターターであるということ。少なくとも「読解に直接結びつくような読み方をしていない」ということです。
「国語読解」って「なんで主人公はそんなことをするわけ?」とか「なんで、こんなこと言うわけ?」とか、要はイチャモンつけなわけです。
国語からきしの理系男子が読書づけとなり、急に国語のテストを上げてくることがあるのはそうした性質によるものではないかと。
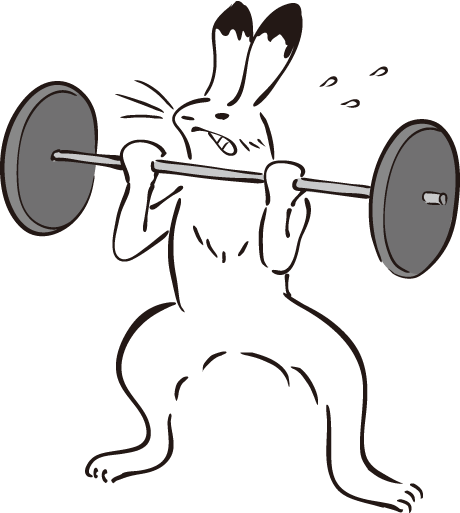
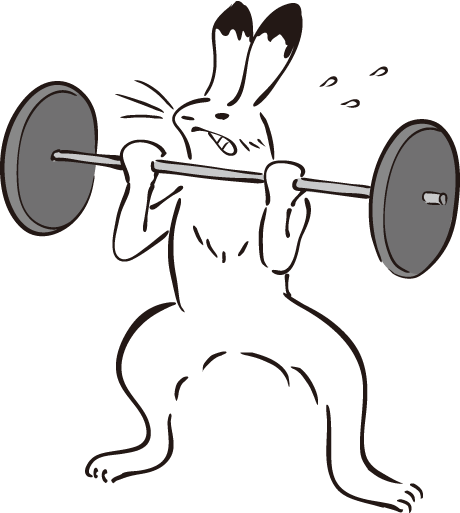
一方、女子に多いと思われますが、純粋に物語世界を楽しむタイプ。素直に共感し、素直に感情移入するタイプですと下世話なイチャモンなど湧いてきません。
これは「4年までは取れたけれど、5年になって国語が前ほど取れなくなった」子どもにも当てはまる場合がありそうです。



そういう考え方もありますね。せっかくの「本好き」が「本嫌い」になる可能性も否めませんがね。
苦手説明文を得点源にする方法
お気づきでしょうが、今回の読書とは主に小説のことを言っています。となれば、読書が好きでも「説明文はからきし」というタイプは多い。逆に物語を読み慣れているからこそ、厄介な部分もあるのです。
何故かといえば、説明文をムードで読んではダメだからです。物語ならば一定の型があり、読み慣れた子には先の展開もだいたいわかるってものです。時間がなく、流し読みしたところで小説慣れした子には実はそれほど影響がありません。
が、説明文を物語のように読んだとしたらどうなることか?
先の展開を憶測し、流し読みしようものなら大いに影響があるでしょう。


また、本人の先入観も問題になります。
読書とは読むほどに、その子にとっての「好み」ははっきりしてくるわけですよ。普段、物語ばっかり読んでいる子ほど説明文が出てきた途端、「あーあ」みたいなね。「こんなつまんないの、読みたくないなー」みたいなね。



そういう可能性もあります。「じゃあ、そもそも読まない方がいいってわけ?」って極論には走らないでくださいよ。
先の表に記したような「読書の効能」も捨ててしまう可能性が大きいわけですから。
ともあれど。
「物語好きで、説明文は苦手」というのは女子によくあるケースです。説明文は感情ではなく論理で読むものですからね。
ここを得意にするには説明文を多く読ませるのが一番ですが、科学ノンフィクションなどを買ってきて「読書として強制する」よりも、説明文の問題を解かせて「勉強として強制する」方が効率はいいでしょう。
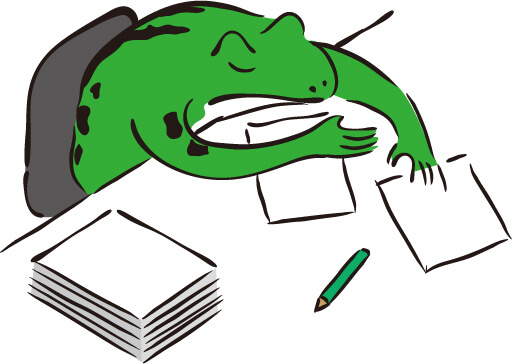
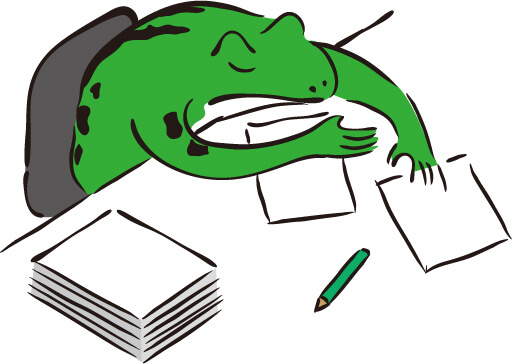
方法は二つ。
1つ目は過去問や問題集にある「説明文」の文章だけを読むこと。
読書の時間ではなく、勉強の時間として読ませるわけです。この際に問題は解かなくて結構。1回につき1文、毎日でなくとも週に2、3回を2、3か月続ければ説明文アレルギーもなくなるはずです。
今が小4、小5なら読むだけでオーケー。仮に上記のような銀本を使うなら志望校は外すとか、女子だけど男子校版を使うなどでも良いと思います。



データを取ったわけではないのですが、過去問の読書は通常の読書に比べ、即効性がある気がします。
入試問題文にはある種の型があるわけです。入試問題ならの特徴的な切り取られ方というのか。
これはオリジナルを読んでもわかりませんね。過去問を読み続けることでパターンは蓄積されます。言葉にはできなくとも、本人の中で見えてくるものが必ずあるはずです。
読書としては邪道ですが、勉強としては正攻法だと思います。
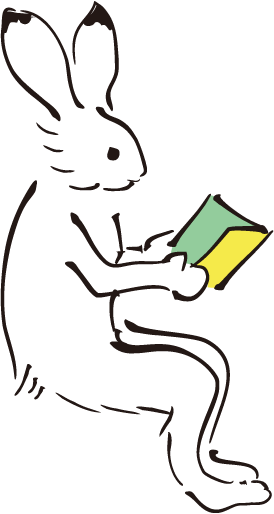
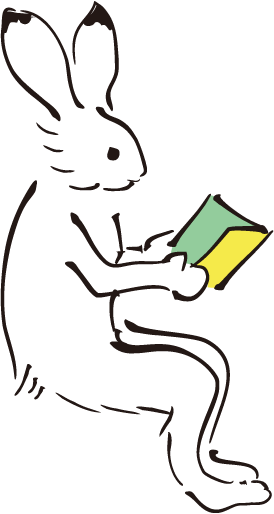
なお、今が小6や小5後半であったり、国語を積極的に攻めたい場合。問題も解きましょう。たくさんやるのではなく選択肢を1日1問で十分です。以下に詳しく書きましたよ。
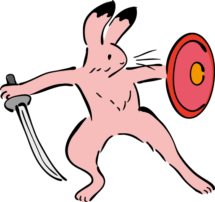
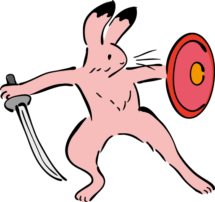
物語文が苦手な場合もこの方法は有効です。
※国語問題なら以下もおススメ!