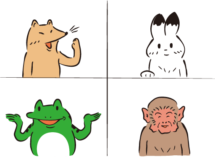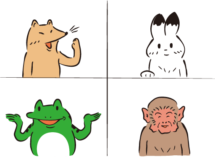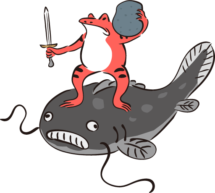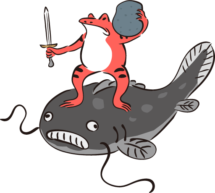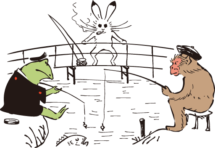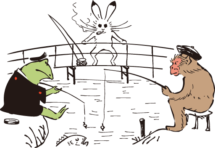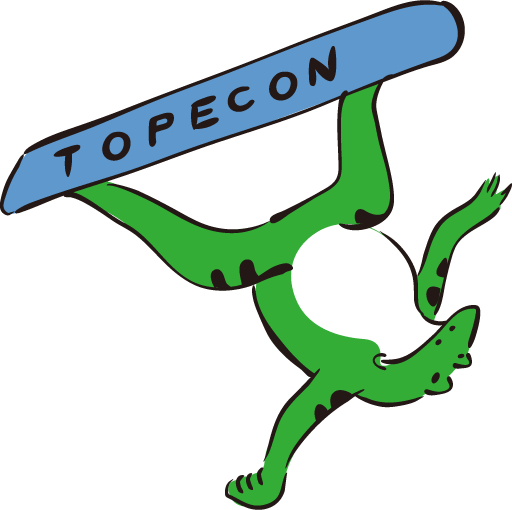「直前期にお子さんは伸びます。特に男子はよく伸びます」
娘の中学受験時代、こんな文言を何度も見かけました。
一般的にいえば「女子はコツコツ長期決戦」「男子は短期集中スピード決戦」みたいなイメージですね。ただ、女子親としてはこの手の話を読むたびに微妙な気分になりました。
 ハンドレッド先生
ハンドレッド先生「受験にジェンダーを持ち込むな!」と言いたくもなりますでしょう。


ともあれど、女子だろうと男子だろうと「直前期になってもエンジンかかる様子もない」「うちの子だけは例外ではあるまいか?」不安な日々を過ごす親御さんは多いはず。
果たして、エンジンのかからない子はどうなるのか?
周囲と自分の体験談から考察したいと思います。
「突然伸びる!」「最後に伸びる!」その前にはグダグダの時期
結論から言いますと、女子でもしっかり伸びました。
周囲の女子も伸びました。女子親ばかりでしたので男子の伸びについては正直よくは知りませんがね。



敢えてジェンダーを持ち込むのであれば「女子がこれだけ伸びたのだから、男子はもっと伸びるはず」。男子親の方々は以下の話に色をつけて解釈しましょう。
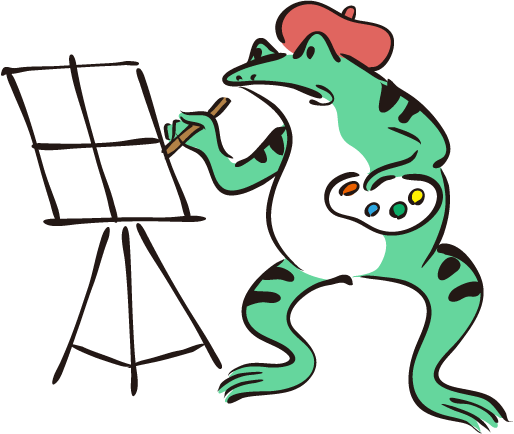
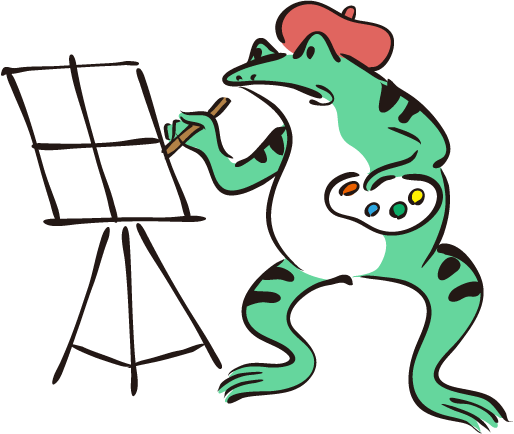
娘の場合、伸びたなと感じたのは冬休み明けでした。
過去問の合格者平均を超えたことのなかった「算数」と「社会」が、突然当たり前のように平均を超え出したのですね。
突然と書きましたが、伸びたきっかけはあるものです。起爆剤は冬休み中の「塾での算数特訓」と「社会過去問の読み込み」でした。
後者について少し説明しますと、第一志望の社会過去問には「出題者の好み」がはっきりありました。漫然と解いている時には気づきませんでしたがね。
それを分析し、間違えた問題に資料をつけ、過去問を参考書化したのです。それを来る日も来る日も読み込む、要は暗記することで正答の勘どころをつかんだわけです。



……言いたいことはわかります。
娘は「塾での算数特訓」を受けた時、思うに「90の貯金」があったのでしょうね。これが「60くらい」だったとすれば起爆する手前で終わっていたかもしれません。
社会もしかり。それ以前に志望校に出やすい記号選択肢などの演習を積んでいたことも功を奏したかと。


忌々しいことに、起爆前夜は、はた目にはわかりません。
今が「60」なのか「90」なのかは、親にはわからないわけです。
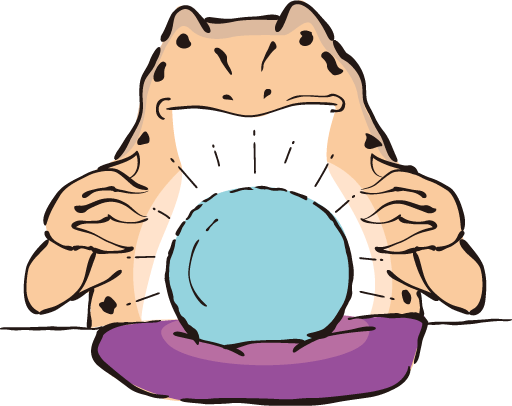
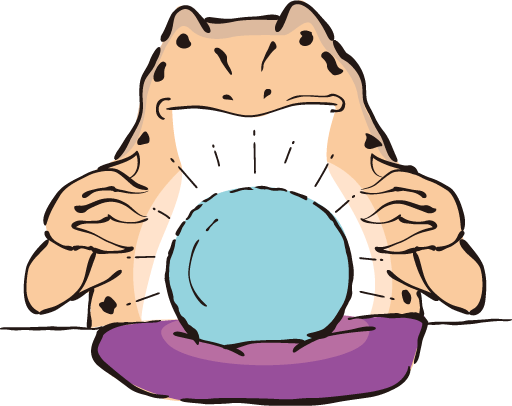
特に入試レベルの問題となると、潜在能力が「90」あっても歯が立たないこともあるでしょう。
「91」あれば解けるものを、「90」がゆえに解けないとかね。
ほんの少しの違いで「停滞時期がえんえん続く」そう思えることもあるでしょう。



仮に見極められる人間がいるとしたら、本人くらいなものだと思います。
しかし、そこは小学生、「できそう!」「もうすぐで、わかりそう!」が信用ならないお年頃。


言えることは、いま結果が出ていなくても腐ることなく続けること。それに尽きます。
「突然伸びる!」の前には必ずグダグダな時期があります。
逆にグダグダな時期なくして「激伸び!」はありえません。当たり前ですが、ずっと良いペースで来た子には劇的な伸びしろはないわけですよ。
経緯を追えば
①「伸びてるんだか、伸びていないんだか、わからない努力時期」
②「起爆剤投入」
③「激伸び!」
という流れでしょうか。
ですから、直前期に「もはやこれまで!」と思ったとしても、「その先へ、その先へ、さらに続けること」が大事なのです。
親が思う「これぞ中学受験生!」はやってこない?
直前期には、子どもの外的変化も気になるでしょう。要するに、親が思う「これぞ中学受験生!」みたいな姿を期待する頃だと思うのです。



四字熟語には詳しいのですね。おっしゃる通り、わき目もふらず、やる気に溢れた受験生像です。
なんとなし、親としては「一心不乱、刻苦勉励の末に激伸び!」みたいな図を想像しがちだと思うのですね。


そこで、ご参考までに、6年後期~直前期の娘の様子を並べてみます。
まず、夏休み明けの9月です。
夏期講習の疲れ、運動会などの学校行事も重なり、一時期は受験する意味すら見失いモチベーションは低下。「これぞ中学受験生!」像はかけらもなくクラスメイトと遊びたくで仕方がない。模試も散々な時期でした。
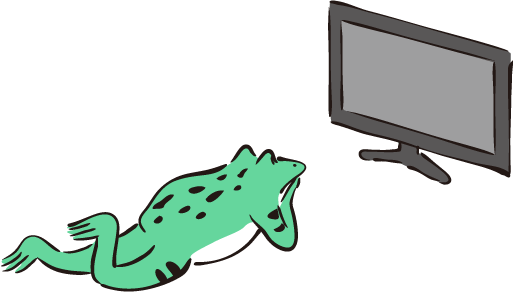
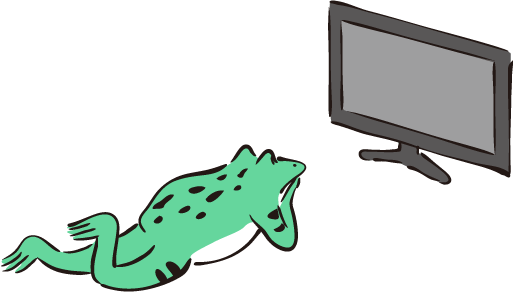
続く10月は「夏の勉強の成果」が模試などに現れてきたため、やる気を取り戻しました。が、早めにはじめた過去問が停滞しはじめ、同時に本人も過去問に飽き始め、なんとなくグダグダに。
一応勉強はしていたものの、親の思う「これぞ中学受験生!」像とはほど遠いものでした。


11月。秋以降、友人との遊びはもちろん、テレビも完全封印。塾の長時間拘束により受験一色といった生活ではありました。
しかし、この期に及んで「これぞ中学受験生!」にはなりませんでした。過去問が取れなくてもあまり気にしていないように見えました。必死さが足りないような気がします。親の方が焦るばかりです。


12月。上記に同じ。
額面で言えば、中学受験生らしい生活です。クリスマスもケーキを食べた後は勉強。塾休みの大晦日も過去問。1月1日も勉強。ああ、しかし、どこまでいっても淡々。わが子はそのまま受験本番を迎えました。



直前期、塾の本番ムードが「激伸び!」スイッチを押すことも
結局。
親である私自身は直前期「これぞ中学受験生の親!」めいてきましたが、肝心の娘の方は「これぞ中学受験生!」めいたことは、ついぞありませんでした。



少なくとも、絶対的なイコールではないようです。
親としてはわかり易く「驚異的な集中力で問題に取り組む姿」を期待したりもするわけですが、そこは結局、本人の性格によるところが大きいのかもしれません。
模試などでは「血気盛ん!やる気満々になり過ぎて空回りする」場合もあるわけですし、やる気みなぎる姿は「激伸び」に必ずしも直結しないのかもしれません。あくまで、想像ですが。
その一方、12月、1月になると塾の雰囲気が怒涛なまでに「本番一色」になってきます。これは家庭で演出できる類のものではありません。
そこに身を投じている子どもたちは「これぞ中学受験生!」的なルックスにはならなくとも、受験に向けてのスイッチが必ず入ってきます。
そのスイッチが「激伸び」につながる子たちも一定数いると思います。
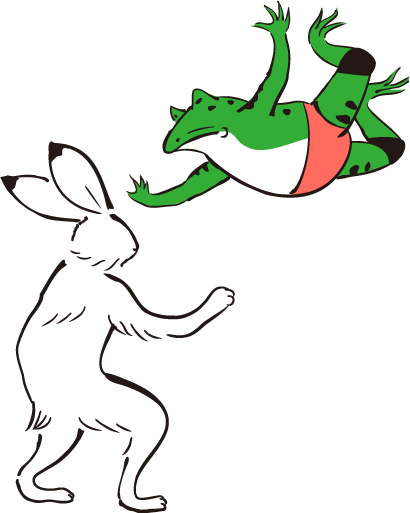
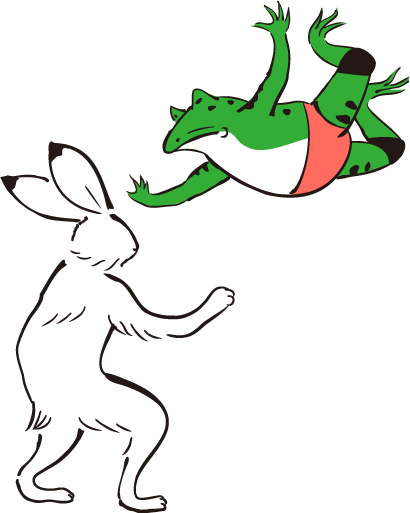
「直前期に学校休むか」問題同様、「直前期に塾を休むか」問題もたびたび取り沙汰されますね。


ただ、「本番ムード」演出において塾の存在は大きいなと思うわけです。
直前期は塾の力が最大化します。4年生から通ったとして3年間でもっとも塾の力が大きいのが6年12月や6年1月。
既に受験範囲を習い終え、各々の過去問対策に取り組む時期です。この時期、個別指導などに集中投下して塾を休む子も増えますね。それで合格を勝ち取る子も多い。
だからといってまったく行かなくなるのも、もったいないなと個人的には思います。
「最後に伸びる」ために親ができることは?



激伸びのプロセスを考えますと、「伸びてるんだか、伸びていないんだか、わからない努力時期」→「起爆剤投入」→「激伸び!」だと思うわけです。
親が介入できるとすれば「伸びてるか、伸びてないか、わからない努力時期」に努力をやめさせないこと。
当たり前すぎる話ですが、結果が出ないからといってすぐに諦めないことですね。
「待つ」とか「信じる」の境地に近くなる感じでしょうか。思うよりも難しいことですが。



ほかにないのか?
「起爆剤投入」に関していえば、わが子の場合、社会に関し最後の最後で親が大きく介入しました。
志望校である吉祥女子の過去問を5年分くらい私が解いて分析したのです。これは大いに効果があった。
やった後は「常時過去問平均点超え」になりましたから。



親にそんな時間がない場合はどうすんのよ
母もハードワーカーで受験直前期も時間が取れなかった方がいましたが、もうそこは金額度外視でアウトソーシングしてましたね、家庭教師に。
で、偏差値70近い学校に逆転合格してました。悪いときは偏差値50そこそこだったりしたのにね。
結局、きれいごとではなく「親の時間投資」か「親のカネ投資か」で世知辛い話になりますが、現実として一定の効果は見込めます。
小学生1人 VS 小学生1人+大人
どっちが強いか?といや答えるまではない。
「スコブル頭脳」の大人がみっちりコツを伝授すれば、逆転合格談はレアではないと今の私は知っている。ただ、カネ勘定に結構な覚悟は必要ですが。


ちなみに、家庭教師にお金投じた場合の大学合格実績ってなぜかいいのね。これは単なる体感ですが。



しかし受験直前期で個別やカテキョを確保できるか
ぶっちゃけ
SS-1
もともと人数少ないからなぁ。
こう言ってはなんですがガチの中受勢がやや下に見がちな(すみません!)大手サービスにこそ穴場があったりする。
たとえば【家庭教師のトライ】
![]()
![]()
とにかく6年で「ヤバい」と思ったら早いうちに資料集めといたほうがよろし。
トライなんかは資料ダウンロードできるから今思いついたら3分後には受け取れますが。
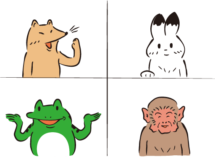
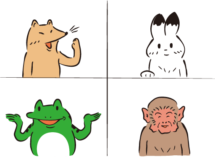
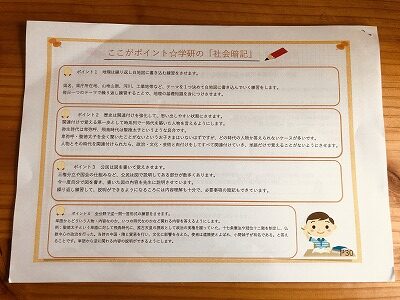
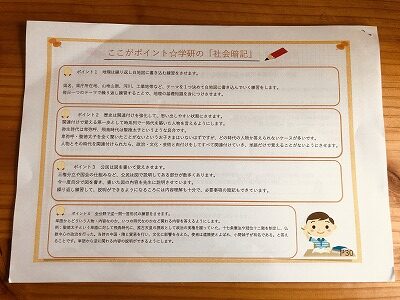
※基礎ポイントながら地味に役立った「学研の家庭教師



ともあれ、まとめだ
伸びる直前、飛ぶ直前は少し下がって一時停止のように思えます。不安にもなる。
けれど、起爆前が「40」だろうと「90」だろうと伸びない生命体はいない!直前期は複利のごとく伸び率だってことは経験上お伝えしておきます。
※当ブログが本になりました!合格率20%でも全勝、凹みメンタルに効きますよ↓